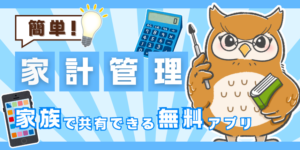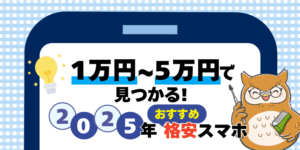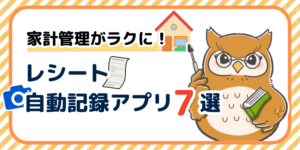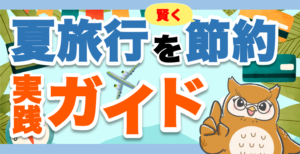「毎日の食事作りが負担に感じる」
「楽をしながらも、節約につながるレシピを知りたい」
忙しい現代人にとって、日々の食事の準備は大きな負担になりがちです。
しかし、作り置きを上手に活用すれば、その悩みは一気に解決に向かうかもしれません。
本記事では、初心者でも取り組みやすい作り置きの基本や、安い食材で作れる節約レシピ、長持ちさせる保存のコツを詳しく解説します。
本記事を読むことで、食事の準備に関する負担を軽減し、家計と心にゆとりを生み出せるようになります。
節約と時短を両立!作り置きが家計と暮らしを楽にする理由

作り置きは単なる調理法ではなく、家計管理と時間管理を同時に改善できる優れた生活習慣です。
計画的に食材を使い切り、調理時間を集約することで、お金と時間の両方に余裕が生まれます。
ここでは、作り置きがもたらす具体的な3つの効果について解説します。
- 食材ロスを減らして食費を賢くカットする
- 毎日の調理時間を短縮して心にゆとりをを生む
- 栄養バランスの整った食生活を手軽に実現できる
食材ロスを減らして食費を賢くカットする
作り置きを実践すると、買った食材を計画的に使い切れるため、冷蔵庫の奥で野菜が傷んでしまうような無駄がなくなります。
さらに、1週間分の献立を考えて必要な分だけ購入すれば、衝動買いも防げるでしょう。
作り置きによって食材を無駄なく活用できれば、食材ロスの削減や計画的な買い物により、ひと月あたり数千円もの節約につながる可能性があります。
浮いた食費は貯蓄に回したり、将来的な大きな買い物の資金にしたりできます。
食材をしっかり使い切る習慣は、家計にも環境にも優しい選択なんだね!
毎日の調理時間を短縮して心にゆとりを生む
仕事や家事で疲れているときに、イチから料理を作るのは大きな負担になります。
作り置きがあれば、温めるだけ、盛り付けるだけで食事の準備が完了するため、調理時間を大幅に短縮できるでしょう。
作り置きを活用することで、1食あたり10分から15分程度、食事の準備期間を短縮できる可能性があります。
空いた時間は家族との会話や趣味、自分のリラックスタイムに充てられます。
時間的余裕が生まれると、精神的なストレスも軽減されるから、生活の質が向上するよ!
栄養バランスの整った食生活を手軽に実現できる
忙しいときほど、簡単な丼物や麺類で済ませがちです。
そこで作り置きがあれば、主菜と副菜を組み合わせた栄養バランスのよい食事を手軽に用意できます。
週末に肉や魚、野菜、豆類など、多様な食材を使った料理を準備しておけば、平日も偏りのない食事が取れるでしょう。
特に野菜の副菜を数種類作り置きしておくと、毎食異なる栄養素を摂取できます。
栄養バランスが整った食生活は健康維持につながり、長期的には医療費の節約にもなるはずです。
作り置きは単なる時短テクニックではなく、家族の健康を守る投資ともいえるね!
初心者でも安心!節約作り置きを成功させる3つのステップ

作り置きをはじめる際は、いきなり大量に作るのではなく、計画的に進めることが継続のカギです。
ここでは、初心者でも無理なく取り組める3つのステップを紹介します。
- ステップ1:1週間の献立をゆるく計画する
- ステップ2:買い物リストを作って無駄買いを防ぐ
- ステップ3:基本の保存容器と便利グッズを揃える
ステップ1:1週間の献立をゆるく計画する
完璧な献立を立てる必要はありません。
まずは、月曜は鶏肉料理、水曜は魚といったように、大まかな主菜の方向性を決めるだけで十分です。
副菜はきんぴらやおひたし、マリネなど、調理法のバリエーションを考えると組み立てやすくなります。
週の途中で予定が変わることも想定し、冷凍できるメニューを1品から2品ほど入れておくと安心でしょう。
また、献立アプリやメモ帳を活用し、家族の予定や好みも考慮しながら柔軟に計画を立てます。
最初は3日分ほどの計画を立て、慣れてきたら1週間分に拡大していくとよいでしょう。
計画を立てるだけで買い物の無駄が減り、調理の見通しが立ちやすくなるよ!
ステップ2:買い物リストを作って無駄買いを防ぐ
献立が決まったら、必要な食材をリストアップしましょう。
冷蔵庫と冷凍庫、常温保存の食材をチェックして、すでに家にあるものは買わないようにします。
スマートフォンのメモ機能や買い物アプリを使えば、買い忘れや重複購入を防げるでしょう。
スーパーでは特売品に目が行きがちですが、リストにないものは本当に必要か一度立ち止まって考えることが大切です。
ただし、予定していた食材より大幅に安い代替品があれば、献立を柔軟に変更するのも賢い選択といえます。
さらに、買い物は週1回から2回程度にまとめることで、交通費や時間の節約にもつながります。
リスト通りに買い物をする習慣が身につけば、月の食費を確実にコントロールできるようになるよ!
ステップ3:基本の保存容器と便利グッズを揃える
作り置きをはじめるにあたって、適切な保存容器は必須アイテムです。
ガラス製やプラスチック製の密閉容器を、大・中・小のサイズで数個ずつ揃えておきましょう。
透明な容器なら中身が一目で分かり、食べ忘れを防げます。
冷凍保存には、密閉できるフリーザーバッグが便利です。
平らにして冷凍すれば、省スペースで保存できるでしょう。
そのほかに、キッチンバサミやスライサー、シリコンスチーマーなどがあると、調理の手間を大幅に減らせます。
近年では、100円ショップでも十分な品質のものが手に入るため、初期投資は最小限で済むはずです。
容器は徐々に買い足せばよいので、まずは手持ちのタッパーから始めても問題ありません。
便利な道具が揃うと、作り置きへのモチベーションも高まるよ!
【食材別】安くて美味しい!節約作り置き鉄板レシピ20選

ここからは、節約作り置きの主役となる、安価で手に入りやすい食材を使った具体的なレシピのアイデアを紹介します。
詳しい手順は省略しますが、調理のポイントやアレンジのヒントを参考に、ぜひあなたのレパートリーに加えてみてください。
- 鶏むね肉・ささみを使ったヘルシーレシピ
- 豚こま切れ肉・ひき肉を使った満足ボリュームレシピ
- 旬の野菜をたっぷり使った彩り副菜レシピ
- 豆腐・厚揚げなどのかさ増しお助けレシピ
鶏むね肉・ささみを使ったヘルシーレシピ
鶏むね肉やささみを使った、ヘルシーレシピを5つ紹介します。
- しっとり鶏ハム
- 鶏むね肉の甘酢照り焼き
- 鶏むね肉のマヨポン炒め
- ささみのごまマヨ和え
- 鶏むね肉のカレーケチャップ炒め
しっとり鶏ハム
鶏むね肉に塩と砂糖を擦り込み、ラップでキャンディ状に包みます。
沸騰したお湯に入れて火を止め、蓋をして1時間放置するだけで完成です。
冷蔵で3日から4日ほど保存できます。
サラダやサンドイッチ、そのまま薄切りにしても美味しく食べられます。
鶏むね肉の甘酢照り焼き
一口大に切った鶏むね肉に片栗粉をまぶし、フライパンで焼きます。
砂糖大さじ2、酢大さじ2、しょうゆ大さじ2、みりん大さじ1を混ぜたタレを絡めれば完成です。
冷蔵で3日から4日程度保存でき、お弁当にも最適です。
鶏むね肉のマヨポン炒め
そぎ切りにした鶏むね肉に酒と片栗粉を揉み込み、フライパンで焼きます。
マヨネーズとポン酢を1対1で混ぜたソースを絡めるだけで、子どもも喜ぶ味付けになります。
冷蔵で3日程度保存可能です。
ささみのごまマヨ和え
茹でてほぐしたささみに、すりごまとマヨネーズ、しょうゆ、砂糖を和えます。
きゅうりやわかめを加えても美味しいのでおすすめです。
冷蔵で2日から3日ほど保存できます。
たんぱく質豊富で低カロリーなのも魅力です。
鶏むね肉のカレーケチャップ炒め
一口大の鶏むね肉に下味を付けて焼き、ケチャップとカレー粉で味付けします。
子どもウケ抜群の味で、冷蔵で3日保存可能です。
ご飯にもパンにも合う万能おかずといえます。
豚こま切れ肉・ひき肉を使った満足ボリュームレシピ
お腹いっぱい食べたい方におすすめのレシピを、5つ厳選しました。
- 豚肉の生姜焼き
- 豚こまボール
- 三色そぼろ
- 肉味噌
- ミートソース
豚肉の生姜焼き
豚こま切れ肉にしょうゆとみりん、酒、すりおろし生姜で下味を付け、フライパンで焼きます。
濃いめの味付けで冷めても美味しく、冷蔵で3日から4日程度保存できるでしょう。
玉ねぎを加えると、さらにボリュームアップします。
豚こまボール
豚こま切れ肉を包丁で細かく叩き、丸めて団子状にします。
片栗粉をまぶして焼き、砂糖としょうゆ、みりんの甘辛ダレで煮絡めれば完成です。
冷蔵で3日、冷凍で2週間ほど保存できます。
三色そぼろ
豚ひき肉を生姜と一緒に炒め、砂糖としょうゆ、みりんで味付けします。
炒り卵と茹でたほうれん草やいんげんを添えれば、彩り豊かな三色丼の具になります。
冷蔵で3日から4日程度、保存可能です。
肉味噌
豚ひき肉をごま油で炒め、味噌と砂糖、酒、みりんで甘辛く味付けします。
豆板醤を加えればピリ辛に仕上がり、ご飯や麺、豆腐にかけても美味しいです。
冷蔵で4日程度保存できます。
ミートソース
豚ひき肉と玉ねぎ、にんじんをみじん切りにして炒め、トマト缶とコンソメで煮込みます。
パスタはもちろん、ドリアやグラタン、パンに挟んでも活用できるでしょう。
冷凍で3週間ほど保存可能です。
旬の野菜をたっぷり使った彩り副菜レシピ
見た目にも鮮やかな副菜レシピを5つ紹介します。
- きんぴらごぼう
- 無限ピーマン
- にんじんしりしり
- ほうれん草のごま和え
- キャベツの塩昆布ナムル
きんぴらごぼう
細切りにしたごぼうとにんじんをごま油で炒め、砂糖としょうゆ、みりんで味付けします。
最後に白ごまを振って完成です。
食物繊維が豊富で、冷蔵で4日から5日ほど保存できる定番副菜です。
無限ピーマン
細切りにしたピーマンをレンジで加熱し、ツナ缶とごま油、鶏ガラスープの素、白ごまで和えます。
箸が止まらない美味しさで、冷蔵で3日程度保存できるでしょう。
にんじんしりしり
千切りにしたにんじんを油で炒め、溶き卵を加えて混ぜ、塩としょうゆで味付けします。
彩りがよく栄養価も高い沖縄の郷土料理で、冷蔵で3日から4日ほど保存可能です。
ほうれん草のごま和え
茹でたほうれん草をすりごまと砂糖、しょうゆで和えるだけの簡単レシピです。
鉄分やビタミンが豊富で、冷蔵で2日から3日程度保存できます。
なお、ほうれん草がなければ、小松菜でも代用可能です。
キャベツの塩昆布ナムル
ざく切りにしたキャベツを塩もみし、水気を絞って塩昆布とごま油、白ごまで和えます。
冷蔵で3日ほど保存できます。
あっさりしていて、箸休めにぴったりです。
豆腐・厚揚げなどのかさ増しお助けレシピ
満腹感を高めたい方におすすめのレシピを、5つ厳選しました。
- 厚揚げの甘辛煮
- 豆腐ハンバーグ
- 厚揚げの肉詰め
- 豆腐のそぼろあんかけ
- 高野豆腐の含め煮
厚揚げの甘辛煮
一口大に切った厚揚げをフライパンで焼き、砂糖としょうゆ、みりん、水で煮絡めます。
生姜を加えると風味が増し、冷蔵で3日保存できます。
ボリューム満点でコスパ抜群です。
豆腐ハンバーグ
豚ひき肉と水切りした豆腐、玉ねぎのみじん切り、卵、パン粉を混ぜて成形し、焼きます。
冷蔵で2日か3日程度、冷凍で2週間保存可能です。
ヘルシーで柔らかい、おすすめレシピです。
厚揚げの肉詰め
厚揚げの中心をスプーンでくり抜き、豚ひき肉に刻んだくり抜いた厚揚げとねぎ、生姜を混ぜて詰めます。
フライパンで焼き、タレを絡めれば見栄えもよい一品になるでしょう。
冷蔵で2日から3日ほど保存できます。
豆腐のそぼろあんかけ
豚ひき肉を炒めて砂糖としょうゆ、みりんで味付けし、水溶き片栗粉でとろみを付けます。
温めた豆腐にかければ、ヘルシーながら食べ応えのある一品になります。
冷蔵で2日から3日程度保存可能です。
高野豆腐の含め煮
戻した高野豆腐を出汁と砂糖、しょうゆ、みりんで煮含めます。
栄養価が高くたんぱく質豊富で、冷蔵で3日から4日ほど保存できるでしょう。
にんじんやしいたけと一緒に煮ると、彩りも栄養バランスもよくなります。
体への負担を減らす!調理が楽になる作り置きの工夫

作り置きは便利ですが、一度にたくさん作るのは体力的に大変です。
調理の負担を減らす工夫を取り入れて、無理なく続けられる方法を見つけましょう。
- 包丁の使用を最小限に!キッチンバサミやスライサー活用術
- 火を使わない!レンジや炊飯器でできる簡単レシピ
- 柔らかくて食べやすい!調理法と食材選びのポイント
包丁の使用を最小限に!キッチンバサミやスライサー活用術
立ちっぱなしでの包丁作業は、意外と体力を消耗します。
そこでキッチンバサミを使えば、座ったままでも肉や野菜をカットでき、まな板も不要で洗い物も減らせるでしょう。
鶏肉や豚肉の薄切り、ねぎやきのこ類はキッチンバサミで十分対応できます。
さらにスライサーを使えば、キャベツやにんじん、大根などを均一に素早く切れるため、千切りやせん切りが必要な料理の時短になります。
また、玉ねぎのみじん切りはフードプロセッサーがあれば数秒で完了し、涙も出ません。
冷凍野菜やカット野菜を活用するのも賢い選択です。
下処理の手間が省けて、調理時間を大幅に短縮できます。
自分に合った道具を探してみてね!
火を使わない!レンジや炊飯器でできる簡単レシピ
火を使う調理は暑い日には特に負担が大きく、コンロの前に立ち続けるのは大変です。
そんな時に大活躍するのが、電子レンジや炊飯器を使ったほったらかし調理です。
レンジ蒸し鶏は、鶏肉に酒と塩を振ってラップをかけ、600Wで5分から6分加熱するだけで完成します。
レンジ肉じゃがも、材料を耐熱ボウルに入れて加熱すれば、煮込む手間なく作れます。
炊飯器は炊飯だけでなく、煮込み料理にも使えて便利です。
炊飯器カレーや炊飯器で作る角煮は、材料を入れてスイッチを押すだけで放置できるので、ほかの作業と並行して調理できます。
レンジや炊飯器でできるレシピは、油を使わないのでヘルシーに仕上がり、後片付けも楽なのがうれしいね!
柔らかくて食べやすい!調理法と食材選びのポイント
家族に高齢の方や小さな子どもがいる場合、食材の硬さや大きさに配慮が必要です。
作り置きでも、少しの工夫で誰もが食べやすい料理を作れます。
食材選びでは、鶏むね肉よりはもも肉、豚ロースよりはバラ肉を選ぶと、冷めても比較的柔らかさを保てます。
野菜は大根やカブ、冬瓜など、煮込むと柔らかくなるものがおすすめです。
調理法では、蒸す・煮るといった、水分を加えてじっくり加熱する方法が、食材を柔らかく仕上げる基本です。
また、野菜を細かく刻んだり、すりおろしたりして加えることで、食べやすさを向上させられます。
とろみをつけたあんかけや、汁気の多い煮物は飲み込みやすく、誤嚥のリスクも減らせるよ!
もっと美味しく長持ち!作り置きの保存術とアレンジ術

せっかく作った料理は、安全にそして最後まで美味しく食べきりたいものです。
そのためには、正しい保存方法と、飽きずに食べ続けるためのアレンジ術を知っておくことが重要です。
ここでは、作り置き生活をさらに充実させるための保存とアレンジのコツを解説します。
- 冷蔵・冷凍の正しい方法と日持ちの目安
- マンネリ防止!簡単味変アレンジアイデア
- 食中毒を防ぐために知っておきたい衛生管理の注意点
- さらにレシピを知りたい方へ
冷蔵・冷凍の正しい方法と日持ちの目安
作り置きの基本は、粗熱を取ってから保存することです。
熱いまま冷蔵庫に入れると庫内の温度が上がり、ほかの食品を傷める原因となります。
密閉容器に入れる際は、空気に触れる面積を減らすため、なるべく隙間なく詰めましょう。
冷蔵保存の目安は、肉や魚の主菜で2日から3日、野菜の副菜で3日から4日程度です。
冷凍する場合は、1食分ずつ小分けにして平らに冷凍すると、解凍時間が短縮でき、使いたい分だけ取り出せます。
冷凍保存の目安は2週間から3週間ですが、なるべく早めに食べ切るのが美味しさを保つコツです。
容器には調理日と内容をラベリングしておくと、食べ忘れを防げるよ!
マンネリ防止!簡単味変アレンジアイデア
同じ料理が続くと飽きてしまいますが、調味料や食材をプラスするだけで、新しい味わいが楽しめます。
たとえば、鶏ハムはそのまま食べる以外にも、サラダに加えたり、サンドイッチの具にしたりとアレンジ自在です。
そぼろは丼やオムレツの具、春巻きの具材としても活用できます。
きんぴらにマヨネーズを加えれば子どもも食べやすい味になり、卵で巻けばお弁当のおかずになります。
カレーは翌日カレーうどんにしたり、カレードリアやカレーパンの具にしたりすると飽きにくいです。
さらにチーズやごま、マヨネーズ、ポン酢、キムチなどを加えるだけで、ガラリと印象が変わります。
少し工夫するだけで、最後まで美味しく食べ切れるようになるよ!
食中毒を防ぐために知っておきたい衛生管理の注意点
作り置きでもっとも気をつけたいのが、食中毒のリスクです。
調理前後の手洗いやまな板や包丁の消毒は、基本中の基本といえます。
特に肉や魚を扱ったあとは、ほかの食材に触れる前に必ず洗いましょう。
保存容器や菜箸も清潔なものを使い、取り分ける際は直箸を避けます。
作った料理は早めに冷まし、常温で長時間放置しないことが重要です。
夏場は特に細菌が繁殖しやすいため、2時間以内に冷蔵庫に入れるようにしましょう。
再加熱する際は中心部まで十分に火を通し、75度以上で1分間加熱することが推奨されています。
少しでも見た目や匂いに異変を感じたら、もったいなくても処分する勇気を持とうね。
さらにレシピを知りたい方へ
ここまで、基本的な作り置きレシピと保存方法を紹介しました。
さらに多くのレシピやアイデアを知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
育ち盛りも大満足!1週間の節約レシピ完全ガイド【まとめ買い&作り置き】
節約作り置きの疑問を解決!よくある質問Q&A
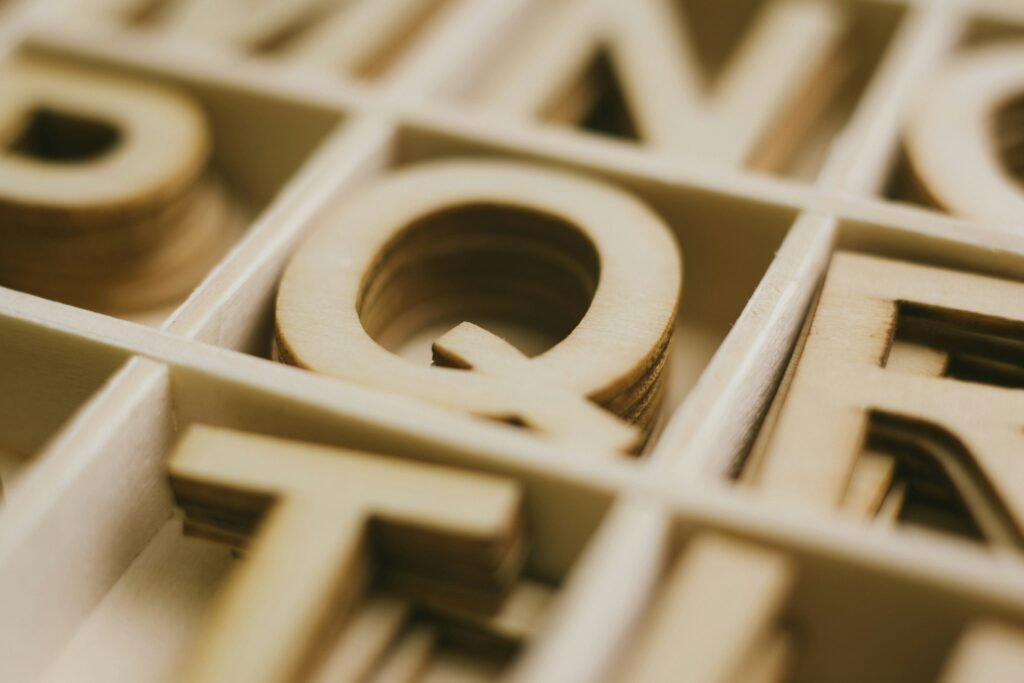
「作り置きをはじめたいけれど、まだ少し不安や疑問がある」そんな方のために、ここでは作り置きに関するよくある質問とその回答をまとめました。
疑問点を解消し、自信を持って作り置きライフをスタートさせましょう。
- 作り置きを続けるコツは?
- 1回の調理時間はどれくらい?
- 育ち盛りの子どもがいる場合のポイントは?
- 栄養バランスが偏らないか心配…
作り置きを続けるコツは?
無理をしないことが最大のコツです。
最初から完璧を目指すと疲れてしまうため、まずは週末に2品から3品ほど作ることからはじめてみましょう。
慣れてきたら徐々に品数を増やしていけば、無理なく習慣化できます。
また、すべての料理を作り置きにする必要はありません。
平日も、簡単な炒め物や汁物を作る日があってもよいでしょう。
さらに家族に手伝ってもらったり、惣菜や冷凍食品を組み合わせたりすることで、負担を分散できます。
作り置きをやらなければならないと考えず、楽をするための準備と捉えると気持ちも楽になるはずです。
1回の調理時間はどれくらい?
作る品数や慣れによって異なりますが、3品から4品程度作る場合は、初心者で2時間から3時間、慣れてくると1.5時間から2時間程度が目安です。
同時進行で複数の料理を作れば、効率的に時間を使えるでしょう。
たとえば、肉を下味に漬けている間に野菜を切る、煮込み料理を火にかけている間に炒め物を作るなど、待ち時間を有効活用します。
炊飯器やレンジを使えば、火元を見ている必要がないため、ほかの家事と並行できるはずです。
最初は時間がかかっても、回数を重ねるうちに手際がよくなり、自然と時短できるようになります。
休日の午前中や、子どもが昼寝をしている時間など、自分の生活リズムに合わせて作業時間を確保しましょう。
育ち盛りの子どもがいる場合のポイントは?
育ち盛りの子どもは食べる量が多いため、かさ増し食材を活用するとよいでしょう。
豆腐や厚揚げ、もやし、キャベツなどは安価でボリュームを出せます。
また、子どもが好むケチャップ味やカレー味、甘辛い味付けのレシピを多めに取り入れると喜ばれるはずです。
唐揚げやハンバーグなどの人気メニューを多めに作って冷凍しておけば、お弁当にも使えて便利でしょう。
栄養面では、野菜を細かく刻んでハンバーグや餃子に混ぜ込む、スープにたっぷり入れるなどの工夫で、苦手な食材も食べやすくなります。
成長期には特にたんぱく質とカルシウムが重要なため、肉や魚、卵、乳製品をバランスよく取り入れましょう。
子どもの意見も聞きながら、家族が満足できるメニュー作りを心がけることが大切です。
栄養バランスが偏らないか心配…
作り置きだからこそ、栄養バランスを意識した献立が立てやすくなります。
主菜には肉や魚、豆腐などのたんぱく質源を日替わりで用意し、副菜には緑黄色野菜や淡色野菜、きのこ類、海藻類など多様な食材を組み合わせましょう。
一汁三菜の形式を基本にすれば、自然とバランスが整います。
冷蔵庫に複数の副菜があれば、その日の主菜に合わせて組み合わせを変えられるため、栄養の偏りを防げるでしょう。
炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラルの五大栄養素を意識し、赤・黄・緑など色とりどりの食材を使うと、見た目にも美しく栄養豊富な食卓になります。
不安な場合は、栄養計算アプリを活用するのもよい方法です。
完璧を目指すよりも、1週間単位でバランスを取るつもりで考えれば、気持ちも楽になるはずです。
まとめ:自分に合った作り置きスタイルで節約生活を楽しもう

作り置きは、食費と時間の節約を同時に実現できる、忙しい現代人にぴったりの生活習慣です。
完璧を目指す必要はなく、自分のペースで無理なく続けることが何より大切です。
まずは、週末に2品から3品ほど作ることからはじめて、徐々に品数や保存期間を調整していきましょう。
作り置きによって浮いた食費やゆとりは、趣味や家族とのひとときや、将来の大きな目標のための貯蓄など、本当に大切なことに使えるようになります。
車の購入資金を貯めたい、旅行に行きたいなど、具体的な目標があればモチベーションも高まるでしょう。
食費の管理は家計改善の第一歩です。
今日から無理のない範囲で、作り置き生活をはじめてみませんか。