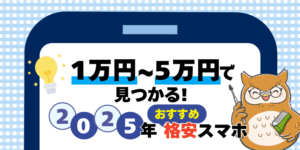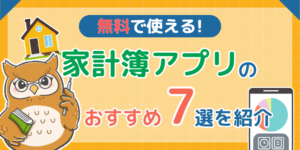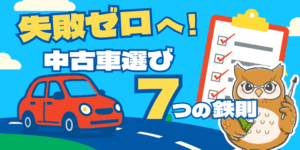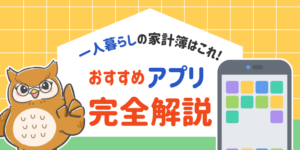「夫婦の生計を同一にするとはどういうこと?」
「夫婦の生計を同一にする基準を知りたい」
税金や保険、介護などの各種手続きにおいて「夫婦の生計が同一かどうか」は重要な判断基準となります。
生計が同一と認められるかどうかで、扶養控除や保険料、各種助成制度の対象となるかが変わるため、正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、夫婦の生計を同一にする際の基準や具体例について分かりやすく解説していきます。
夫婦の家計を同一にする際の基準は?

夫婦の家計を同一にする際の基準には、下記の3つがあります。
- 生活費の共有があるか
- 居住場所が同じであるか
- 経済的な扶養関係があるか
それぞれの要件について、順番に見ていきましょう。
生活費の共有があるか
生計が同一とみなされるかどうかは、夫婦の間で生活費を共有しているかが重要なポイントです。
たとえば、どちらか一方の収入で家賃や水道光熱費、食費などの生活費をまかなっている場合、生計は同一とみなされます。
共働きの場合でも、生活費を一方にまとめているケースや、口座を共有しているケースも同様です。
生活費を独立して管理している場合は、形式上は夫婦であっても生計が別と判断されることがあります。
家計をひとつにまとめて管理しているかどうかが、ひとつの判断基準になるんだね!
居住場所が同じであるか
夫婦が同じ住居で暮らしていることも、生計同一の判断材料となります。
たとえ扶養控除などを申請する際に婚姻関係があっても、別居している場合は理由の確認が必要です。
単身赴任など、物理的な距離があっても生活費の仕送りなどをしていれば、生計が同一と認められることもあります。
同じ建物内で暮らしていても、家計が別々なら生計を一にしない家族に該当するよ。
経済的な扶養関係があるか
収入のある配偶者が、収入のない配偶者を経済的に支えている関係であれば、生計は同一と判断されやすくなります。
たとえばパートナーが専業主婦(夫)の場合や、出産や育児、病気などの事情で収入がない場合でも、扶養関係が明確であれば問題ありません。
反対に、夫婦それぞれが独立して生活費をまかなっている場合、生計が別とされる可能性があります。
こちらも、金銭的な支えがあるかどうかをチェックしたうえで判断されるんだね!
家計を同一にする夫婦の具体例

夫婦の家計を同一にする際の基準について解説しましたが、いまいちピンときていない方もいるでしょう。
ここからは、家計を同一にする夫婦の具体例を3つ紹介するので、自分事としてとらえてみてください。
- 夫が主たる収入源で妻が専業主婦の場合
- 夫婦共働きで生活費を共有する場合
- 別居中でも生活費の送金がある場合
夫が主たる収入源で妻が専業主婦の場合
もっとも分かりやすいのが、夫が働いて妻が専業主婦というケースです。
この場合、生活費は夫の稼ぎから全額支払い、妻は収入がなく完全に扶養されている関係となります。
このような夫婦は、生計が同一であると明確に判断され、扶養控除などの税制上の優遇も受けられます。
確定申告や年末調整をおこなう際には、住民票や源泉徴収票などで確認が取れるよう準備しておきましょう。
パートナーの収入がなければ、扶養されている状態だとすぐに分かるね!このケースなら迷わずに判断できるね。
夫婦共働きで生活費を共有する場合
共働き夫婦でも、生計が同一とされるケースは多くあります。
たとえば、夫婦それぞれの収入をひとつの共同口座に集め、そこから家賃や水道光熱費、日用品費などの共通支出をまかなっているケースです。
このように経済的に協力し合って生活している状態であれば、生計が同一だと判断されます。
ただし、すべての会計を別にして生活しているとみなされた場合、生計は同一ではないと判断される可能性もあるから注意してね。共同口座については、こちらの記事で詳しく解説しているから参考にしてみてね!

別居中でも生活費の送金がある場合
夫婦が物理的に離れて暮らしていても、生活費を一方がもう一方に送金している場合、生計が同一と判断されることがあります。
たとえば、単身赴任中の夫が妻に仕送りしている、またはその逆も同様です。
別居しているからといって、生計も別とは限らない点に注意しましょう。
税務署に申告する際は、銀行振込の明細などを用意して、送金の証拠を提出できるようにしておくとスムーズだよ!
世帯分離をする方法とは?

前提条件ですが、夫婦が同じ住所で生活している場合、世帯分離は基本的にできません。
しかし、一定の条件を満たすことで、世帯分離が認められるケースもあります。
ここからは、夫婦間で世帯分離をする方法や注意点について解説していきます。
- 世帯分離とはどういう意味?
- 世帯分離の手続き方法
- 世帯分離をおこなう際の注意点
世帯分離とはどういう意味?
「世帯分離」とは、同じ住所に住んでいる人同士でも、住民票上の世帯を分けて別世帯として登録することです。
たとえば、夫婦が同居していても、役所に申請すれば夫世帯と妻世帯のように分けて扱われるようになります。
世帯分離をおこなうと、介護保険料や国民健康保険料が軽減されたり、各種助成制度の対象となったりすることがあります。
ただし住民票上で分かれていても、実際の生活実態が生計同一であれば、扶養関係や課税区分には影響が出ない場合もある点に注意が必要です。
利用する制度によって違いがあるから、事前に確認しておくと安心だね!
世帯分離の手続き方法
世帯分離をおこなうには、住民登録をしている市区町村の役所で世帯変更届(住民異動届)を提出する必要があります。
必要書類の提出により、夫婦のうち一方を新しい世帯主とし、既存の世帯から分けて新たな世帯として登録されます。
世帯分離には特別な理由が必要なわけではなく、住民票の異動とは異なり住所の変更も不要です。
手続きは比較的簡単で、窓口で所定の用紙に記入し、本人確認書類などとともに提出すればその場で完了します。
ただし、自治体によっては必要な書類が異なる場合もあるため、事前にホームページなどで確認しておくのがおすすめです。
世帯分離の手続きの際、役所の窓口で生計が別であることを確認されるケースもあるよ。所得証明書などがあるとその場で証明できるから、用意しておくとスムーズに手続きできるよ!
世帯分離をおこなう際の注意点
世帯分離は手続き上は簡単でも、税制や保険料、介護サービスなどの各制度に与える影響を考慮する必要があります。
たとえば、住民税の均等割や介護保険料が減額される可能性がある一方で、扶養控除に悪影響を及ぼす場合もあります。
また、生活実態が生計同一と認められる場合、制度上は扶養関係が継続して扱われるため、単純に世帯を分けただけで有利になるとは限りません。
世帯分離を検討する際は、制度のメリットとデメリットを正しく把握してから判断することが重要です。
税金の軽減を目的とした世帯分離を希望する場合、税務署から疑念を持たれる可能性があるよ。また、結果として費用負担が増えることも考えられるから、安易な気持ちで世帯分離をおこなわないようにしようね。
まとめ
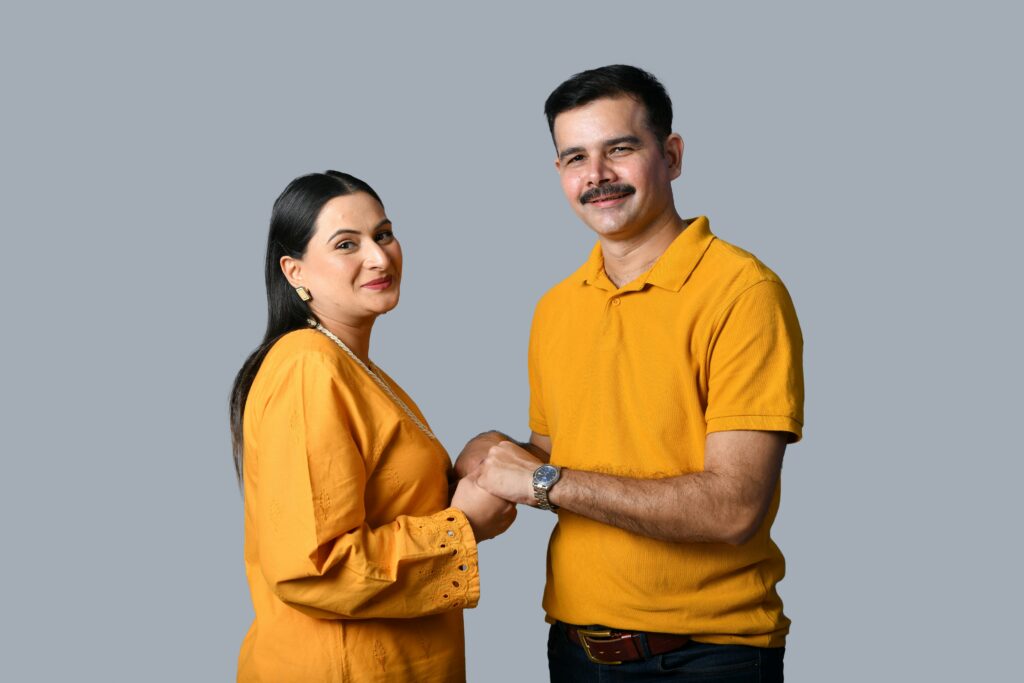
夫婦が生計を同一にしていると見なされるかは、下記の3つの基準によって判断されます。
- 生活費の共有があるか
- 居住場所が同じであるか
- 経済的な扶養関係があるか
専業主婦(夫)のケースはもちろん、共働きや別居中でも条件を満たせば生計同一と認められます。
一方で、税制や保険料を考慮して世帯分離を選ぶことも可能ですが、手続きや制度の仕組みを理解しておくことが重要です。